こんにちは、灯子です。
今年も、残すところ2か月余りとなりました。
そろそろ勤務先から、年末調整のお知らせが届くころですね。
ところで、あなたは、令和7年の税制改革についてご存知でしょうか?
わたしは、ふるさと納税をしていることもあり、早めに今年の税金を確認しておきたくて、令和7年分の所得をざっくり試算してみました。
昨年の給与収入と今年の給与収入は、さほど差はありませんが、
税制改正があったために、昨年に比べて、今年はかなり減税されることに気づきました。
でも、この所得税減税って喜ぶべきことなのでしょうか?
わたしは、この減税額を知って、正直、
「で?」
って思いました。
それは、何故かをお伝えしたいと思います。
✅ 源泉徴収表読み方ガイド
このお話を続ける前に、まず、源泉徴収表の見方についてまとめてみたいと思います。
税金の話って、数字よりも“用語”でつまずくんですよね。
給与収入?給与所得?所得控除?…似てるようで意味が違う。
だから、灯子はいつまでたっても計算式を覚えられないのです💦
この記事では、まず、源泉徴収表に書かれている言葉の意味を確認してから、数字の話に進みます。
✅ 源泉徴収票を準備しよう(令和6年度分でOK)
昨年の源泉徴収票をお手元に置きながらひとつづつ確認していきましょう。
🔹 支払金額とは?
会社から支払われた金額。(給与、賞与、各種手当の合計額)
🔹 給与所得控除後の金額とは?
給与所得。
支払金額から「給与所得控除(みなし経費)」を引いた金額。
実際に税金の計算に使われる“もうけ”の部分。
※給与所得控除とは、給与収入から差し引かれる“みなし経費”のようなもの。控除額が増えることで、課税所得が減り、結果的に所得税額が軽減されます。
🔹 所得控除の額の合計額とは?
税金を軽くするために所得から差し引ける金額。
給与所得控除以外の、厚生年金保険料、健康保険料、雇用保険料など1年間の合計支払額と、基礎控除、配偶者控除、扶養控除などを合わせた金額。
※給与所得控除は“収入からの控除”、所得控除は“給与所得からの控除”です。
✅ 控除の位置づけと違い
給与所得控除と所得控除がよく似ていてるので、以下のように違いをわかりやすく表にまとめてみました。
| 項目 | 対象 | 目的 | 控除後に残るもの |
|---|---|---|---|
| 給与所得控除 | 給与収入 | みなし経費として差し引く | 給与所得 |
| 所得控除 | 給与所得 | 個人事情に応じて差し引く | 課税所得 |
🔹 源泉徴収税額とは?
源泉所得税と復興特別所得税の合計額。
※「源泉徴収」とは、給与や報酬から税金をあらかじめ差し引いて、従業員の代わりに会社が納める仕組みです。
✅ 給与所得者の源泉徴収税額計算の流れ
言葉の意味を理解したら、次に源泉徴収税額の計算の流れを見ていきましょう。
源泉徴収税額を計算するには、新たに「課税所得」についての理解が必要になってきます💦
- 課税所得の計算
課税所得= 給与所得 – 所得控除の合計
※給与所得控除後の金額が“給与所得”です。 - 源泉所得税の計算(所得税)
源泉所得税=課税所得 × 税率 - 控除額
「税率」と「控除額」は課税所得に応じた7段階の累進税率表に基づきます。 - 復興特別所得税の計算
復興特別所得税= 所得税額 × 2.1% - 合計所得税額(源泉徴収税額)
合計所得税額=源泉所得税+復興特別所得税
2025年(令和7年)現在の日本の所得税率は、課税所得に応じて7段階に分かれています。以下の表をご覧ください。
| 課税される所得金額(円) | 税率 | 控除額(円) |
|---|---|---|
| 1,000 ~ 1,949,000 | 5% | 0 |
| 1,950,000 ~ 3,299,000 | 10% | 97,500 |
| 3,300,000 ~ 6,949,000 | 20% | 427,500 |
| 6,950,000 ~ 8,999,000 | 23% | 636,000 |
| 9,000,000 ~ 17,999,000 | 33% | 1,536,000 |
| 18,000,000 ~ 39,999,000 | 40% | 2,796,000 |
| 40,000,000 以上 | 45% | 4,796,000 |
参考:国税庁 所得税の税率
令和7年度税制改正とは?
令和7年(2025年)の税制改正では、所得税・住民税に関する控除制度が見直され、特に給与所得者や低〜中所得層にとって減税効果が期待される内容となっています。
🧾 主な改正ポイント
| 改正項目 | 内容 | 対象・影響 |
|---|---|---|
| 基礎控除の段階加算(令和7・8年限定) | 所得が低いほど控除額が増加(最大95万円) | 合計所得132万円以下の人は控除額が拡大 |
| 給与所得控除の最低保障額引き上げ | 55万円 → 65万円に | 年収190万円以下の給与所得者に恩恵あり |
| 課税所得が減る | 控除額の増加により、課税対象が縮小 | 結果的に所得税額が減る人が多い |
| 住民税にも波及 | 所得税控除の影響が住民税にも連動 | 控除額に応じて住民税も軽減される可能性あり |
参考資料:
国税庁「令和7年分 基礎控除の見直し」
財務省「令和7年度税制改正大綱」
🧾 基礎控除の改正内容(令和7・8年)
今回の改正内容の目玉の一つ(?)が基礎控除の改正。
特に、パート勤務の方には影響が大きいのではないでしょうか。
| 合計所得金額 | 基礎控除額(令和7・8年) | 基礎控除額(令和9年以降) |
|---|---|---|
| 132万円以下 | 95万円(+37万円) | 95万円(恒久化) |
| 132万超~336万円以下 | 88万円(+30万円) | 58万円 |
| 336万超〜489万円以下 | 68万円(+10万円) | 58万円 |
| 489万超〜655万円以下 | 63万円(+5万円) | 58万円 |
| 655万円超〜2,350万円以下 | 58万円(加算なし) | 58万円 |
参考:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)
- 2,350万円超の高所得者は段階的に控除が減少し、最終的にゼロになります。
- この改正は、令和7年・令和8年の2年間限定措置であり、令和9年以降は縮小または恒久化される部分もあります。
🧾 給与所得控除の改正内容(令和7年)
給与所得控除は、最低金額55万から65万円に引き上げられました。
| 給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
| 1,900,000円まで | 650,000円 |
| 1,900,001円から3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
| 3,600,001円から6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
| 6,600,001円から8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
| 8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
- 改正されたのは、収入190万円以下の人まで
- それ以上の収入帯(190万円超)は、令和6年以前と同じ控除式が継続
- 最低控除額が55万円 → 65万円に引き上げられたのが最大の変更点
ご自分の給与所得控除後の金額をお知りになりたい方は、下の表から簡単に探すことができます。
※「給与所得控除後の金額」=給与収入「支払金額」-給与所得控除
頭を使った後は、ふわふわのスナッフルズ「オムレット」🧁
🧩 減税なのに「で?」と思った理由
税制改革によって、今年の所得税は昨年よりもかなり減ることがわかりました。
でも、その金額を見て、わたしは正直「で?」と思ったのです。
なぜなら、その減税額で、今の生活が潤うか?
といったら、まったく潤わないからです。
🔍 控除が増えても、手取りは劇的に変わらない
たとえば、給与収入が昨年とほぼ同じで、控除が増えたことで課税所得が減ったとします。
その結果、所得税が1万〜3万円ほど減ったとしても、月々の手取りが数千円増えるだけ。
さらに、物価高が加速しており、月々の数千円など、あっという間に吹き飛んでしまう💦
控除額よりも、実際に手元に残るお金のほうが大事!
③ 消費税のリアルな負担:誰でも確実に払っている
では、消費税の場合はどうでしょうか。
わたしと同じように、働くシニア女性の食費・日用品・サービスなど、日々の支出にかかる年間消費税負担額は、ある調査では約26万円前後(推定)と算出されています。
もちろん、平均値なので、人によっては、そこまで払ってないよという方もいらっしゃるでしょう。
わたし自身も、さすがにここまで払っていないと思ったんですけど、通信費や光熱費などあらゆるものに課税されていることを考えると、あながち見当違いな数字ではないように思います。
🔍 消費税の「逆進性」とは?
ちなみに、消費税には「逆進性」という性質があります。
これは、所得が低い人ほど、生活費に占める消費税の割合が高くなるということ。
たとえば、月20万円の生活費のうち、食費・日用品・光熱費・通信費などに消費税がかかると、
年間で約26万円前後の消費税を負担している計算になります。
一方、高所得者は収入に対して生活費の割合が低いため、消費税の負担感は相対的に小さくなるのです。
つまり、消費税は「誰でも払っている税金」だけど、負担感は人によってまったく違うということ。
だからこそ、
消費税の減税は“誰にでも届く”という意味で形式的に公平
であり、
生活が苦しい人ほど効果が大きいという意味で実質的にも公平性がある
と、わたしは思うのです。
まとめ:税の計算方法、使い道を知ろう
いかがでしたか?
税計算はややこしくて、
ついつい会社任せにしてしまっているけど、自分で計算してみることで、今の税制システムを理解することができます。
わたしは、今回所得税の概算を計算したことで、所得税減税はさほど国民の生活に影響はないと感じました。
それよりも、老若男女、子供からお年寄りまですべての人が恩恵を受けることができる”消費税減税”をすぐに取り入れるべきだと思います。
所得に関係なく、誰でも負担している税金であり、給付金と違って面倒な手続きもない、消費税減税の方が“即効性”と“公平性”があると思います。
財源がない?
だって、バラマキ外交
裏金工作
一杯やっていたじゃないですか。
無駄なんかいくらでもあると思いますがね。
それに、物価が上がってることで税収は恐ろしく増えているんですから、
後は、やるかやらないかだけでしょう?
それを後押しできるのが、わたしたち国民一人ひとりが
税金がどのように徴収され、どのように使われているのかを知り、見届けていくことが、社会を動かす力になると思います。
2025年度の税収は78.4兆円と過去最高を更新する見込みで、消費税だけでも約25兆円に達するとされています。
これだけの税収がある今こそ、生活者に直接届く減税策が求められているのではないでしょうか。
日本の歳入と税収の推移【2025年最新】6年連続過去最高を更新する税収の背景
※この記事は10月24日時点に書かれたものであり、高市政権における政局次第では、減税対策が変更されるかもしれません。
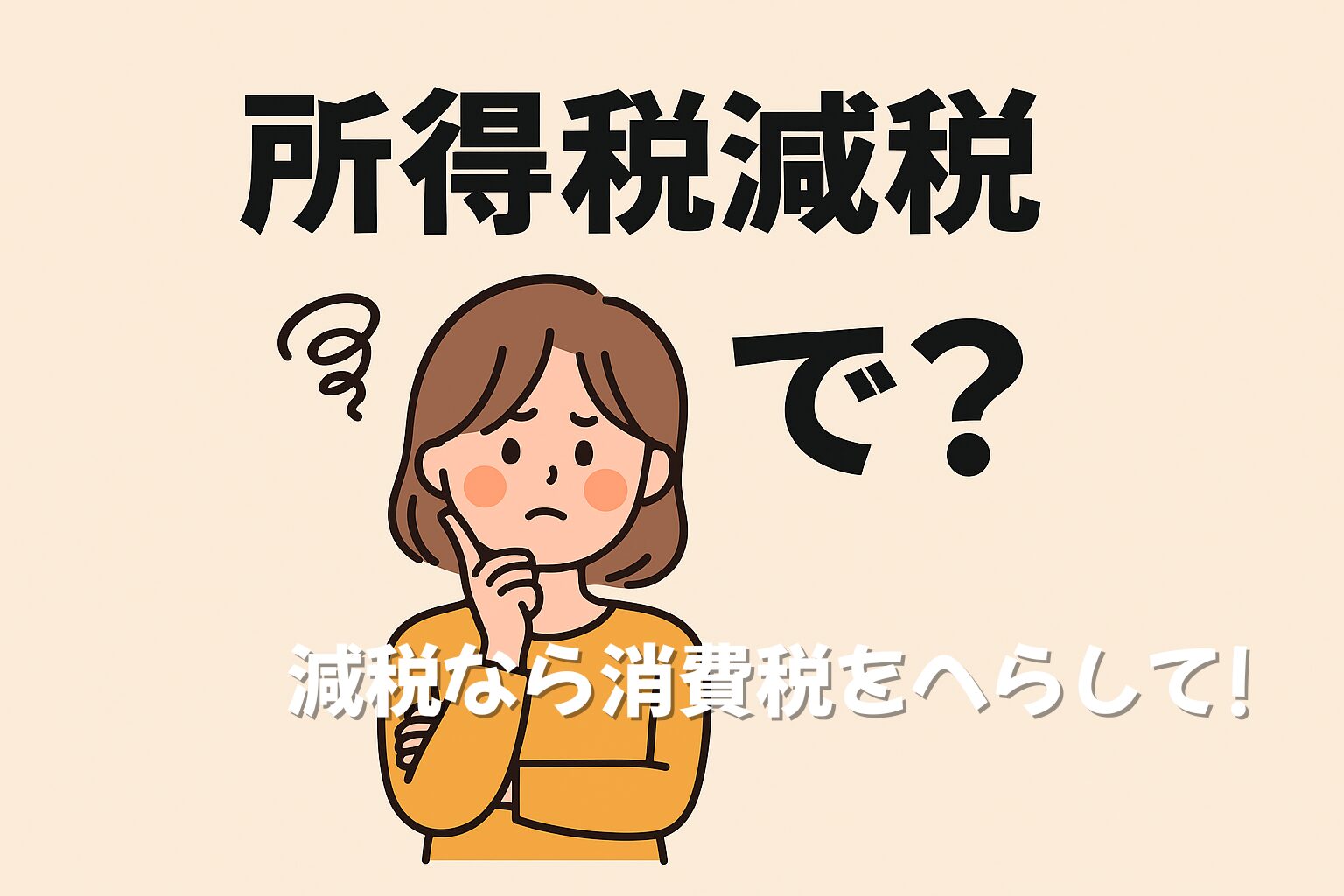



コメント